
-
居宅介護支援事業所Lucky
介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるように、ケアプラン(サービス計画書)の作成やサービス事業者との調整を行い、自宅で生活できる様に支援します。
要介護認定を受けた方が、自宅で介護サービスを利用しながら生活できるように支援します
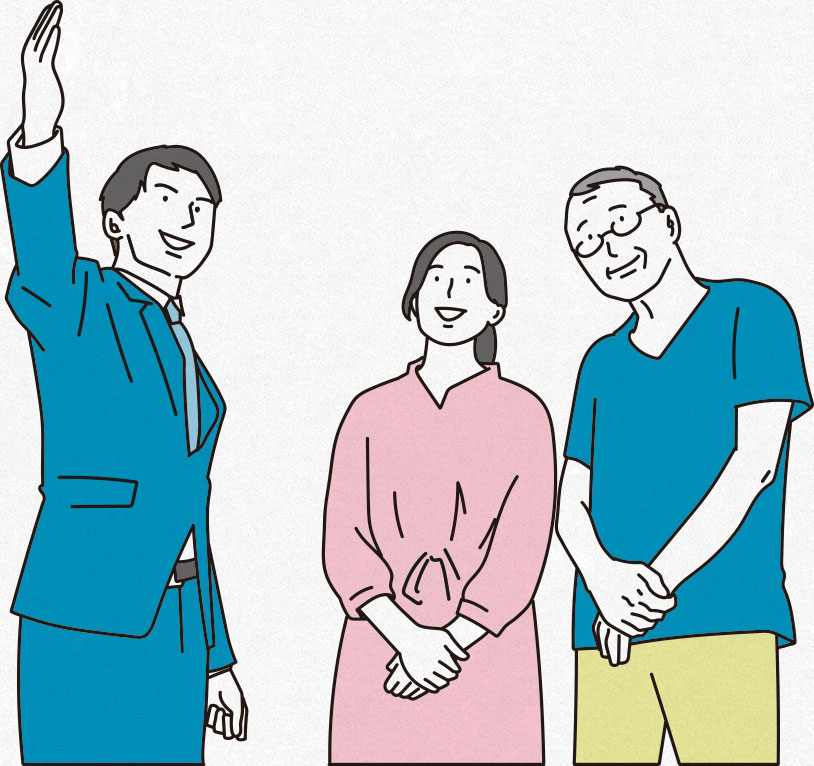
寄り添う支援で安心した生活
大切にしていること
ご本人様ご家族様の思いを大切にし、迅速、丁寧に対応することを心がけております
- 以前より体が動かなくなり生活に不安を感じるようになった…。
- 仕事をしているのだけど両親の介護で日々不安を感じている…。
- 一人暮らしで今後どうして良いのかわからない…。
生活面や身体面でのお困りのことがある場合、直ぐに自宅へ訪問し、直接お話を聞き、具体的なサポートを説明させていただきます。
-
気持ちに寄り添って話を聴きます
-
利用者本人と家族の両方に対して公平性を持ちます
-
介護サービスの専門的な知識を持っています
-
納得できるケアプランの作成をします
-
理解しやすい説明をします
-
介護サービス以外の社会資源についての知識を有します
-
守秘義務や法的に必要のあることをきちんと守ります
-
連絡が取りやすい環境にします
Luckyの居宅サービス
-
01
お問い合わせ介護のことについて、まずはお電話、または直接ご来訪頂き、ケアマネジャーにご相談ください。介護認定を受けていない方は、必要に応じて認定申請をして頂きます。市区町村の介護険課窓口に書類提出が必要ですが、ケアマネジャーがご本人様やご家族様に代行して申請いたします。
-
02
ケアプラン作成ご相談を受けてから、必要に応じてケアマネジャーが直接訪問をさせて頂き、ご本人様、ご家族様の心身の状況、家庭環境などの現状を専門的な立場からしっかりと把握し、どのようなサービスが必要なのか、生活スタイルに合ったサービスをどれくらい利用し、どのような生活になるのかイメージできるようにわかりやすくご説明致します。サービスが決まったら ケアプラン(介護サービス計画書)を作成致します。
-
03
サービス調整利用開始前に、ご自宅にてご本人様、ご家族様、利用するサービス事業所とのサービス担当者会議を行い、サービス内容などを話し合い、お客様の状態に最適な受け入れ態勢を整えます。
-
04
介護保険サービス開始各サービス事業者と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスを利用します。 原則として費用の1割~3割が利用者負担となります。(介護保険制度改定により負担割合が変更になる場合がございます)
-
05
モニタリング開始サービスを開始してからも何か困ったことがあれば、その都度ケアマネジャーに相談してください。相談費用は無料です!また、月1回は必ずご本人様宅を訪問させて頂き、サービスの利用状況を確認し、必要に応じていつでもサービスを調整します。
-
ケアマネジャー
利用料要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はございません。(介護保険制度改定によりケアプラン作成料金が変更になる場合がございます)
豆知識
-

居宅介護支援とは
居宅介護支援では、可能な限り自宅で日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、ケアプランを作成します。ケアマネージャーはご利用者様・ご家族様の、心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するた めのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
-

ケアマネジャーとは
要支援・要介護認定該当者やご家族様からの相談を受けて、日常生活を送るために必要となる福祉サービス等を適切に利用することができるように★申請手続き代行★状況把握★目標設定などを考慮した上でケアプランを作成し、その計画に基づいて適切なサービスを提供できるようにデイサービスやヘルパー、訪問看護の事業者などと連絡・調整を行います。
-

ケアプランとは
ご利用者様の状況や要望にもとづいて「これからどのような生活を送りたいか」などの目標を設定し、その目標にむけて利用するサービスの種類や頻度を決めた利用計画書のことです。
-

ケアプランへの取組み
地域に根づき地域でいつまでも生活できるように支援していきます。 ご利用者様、ご家族様が楽しくなるようなプランを一緒に考えていきます。 いつでも迅速、丁寧に取り組んでまいります。
実際の相談ケース

- 相談の経緯
- 解離性大動脈瘤のため入院となり、食事摂取困難で胃ロウの増設となりました。退院に際し、妻との二人暮らしは困難が予想され、娘も近くに住んではいるが仕事もあるし…自宅に戻ってからどうしたらよいのか…とご家族様より相談がありました。
ケアマネジャーの対応
先ずは、ケアマネジャーが病院を訪問し、ご本人様、ご家族様の状況を聞き取りながら、介護保険利用の主旨を伝えました。退院に向けての相談回数を重ねる中で、病院のメディカルソーシャルワーカーにも加わって頂き、医療と介護の連携を密に行いながら、万全の体制退院できるようにケアマネジャーが先頭に立って話を進めました。そして、退院前には事前相談で思い描いた在宅生活を実施できるように、各介護サービス事業者がしっかりと体制を整えました。
-
step1
ケアマネジャーが病院を訪問し、ご本人様、ご家族様の状況を聞き取りながら、介護保険利用の主旨を伝えました。
-
step2
病院のメディカルソーシャルワーカーにも加わって頂き、医療と介護の連携を密に行いながら、万全の体制で退院できるように話を進めました。
-
step3
退院前には事前相談で思い描いた在宅生活を実施できるように、各介護サービス事業者がしっかりと体制を整えました。
-
step4
被介護者・介護者様共に、退院前に今後の介護内容が明確になり、心身の負担を軽くすることが出来ました。また、退院後にスムーズに介護サービスを利用することができました。
退院に際して利用したサービス
-
①福祉用具
立ち上がり、起き上がり、オムツ交換、経管栄養など、様々場面において介護用ベッドが必要との判断となり、退院前日に自宅へ搬入となりました。
- 利用者さまのお声
- 実際に使用してみて、立ち上がる際に高さを調整できるので安心してスムーズに立ち上がる事ができた。経管栄養時に上半身を起こさなくてはいけないが、リモコン一つで起き上がる事ができるので負担軽減できました。
-
②訪問看護師
退院後も医療的視点から栄養状態(経管栄養)や身体状況の観察、家族への指導や助言が必要と判断され、看護師による自宅訪問の利用となる。退院後2週間は毎日看護師が訪問となった。
- 利用者さまのお声
- 看護師が医療のことや食事のことなど、わからないことはなんでもやさしく教えてくれたのでいつも心強かった。
-
③訪問リハビリ
入院生活が車椅子だったため、下肢筋力が低下している状態であった。退院後もしばらくは車椅子での生活が予想された。そのため、ベッドからの起き上がり、立ち上がりなどの起居動作からリハビリを始める。
- 利用者さまのお声
- リハビリをやってもらうと本人の体の動きも良くなり、介護する側の負担の軽減になった。一番は本人が少しずつ動けるようになり生活に意欲も湧いてきた。
介護サービスの導入をしてからの在宅生活
-
point1
退院してからも毎月ケアマネジャーが自宅を訪問し、困っていることやサービスが適切に 行われているかをご本人様、ご家族様と一緒に話し合いました。
-
point2
ご本人様の生活意欲とご家族様のサポート、介護と医療の連携がうまく取れ、約9ヶ月で何も使わずに歩けるようになるまで回復し、今では介護保険を利用せずに家族のサポートを受けながら生活できるようにまでなりました。